小学二年生になる健二には、たった一つだけ、でも彼には重大な悩み事がある。
鉄棒で逆上がりが出来ない事だ。
体育の時間はむしろ大好きである。基本的にスポーツは得意だ。だからこそ、鉄棒が出来ない自分を恥じ、運動オンチだと周りに思われるのは、八歳の少年のプライドをズタズタにするには充分な事だった。
放課後に人知れず練習していた事もある。だが、いくら努力してもちっとも進歩しない。そんな日は半ベソを掻きながら家に帰る。大好きなアニメ番組も彼の心を慰める事は決して出来ない。
授業で鉄棒があるとき、健二は決まって腹痛を起こす。
サボりではない。本当に拒絶しているのだ。
しかし根がしっかりしている健二はその事を先生には云わない。
そして、特訓が始まる。
何回やっても、絶対出来ない。彼にとって補助つきで逆上がりが出来ても、それは出来てないのと何ら変わらなかった。
先生は、もう少し、あとちょっと、と呪文を唱える。無駄な事だ。
そして、さすがに付き合うのに嫌気がさすと、先生は決まって言うのだった。
意識が足りない
―イシキ―イシキ―
健二には、ただこだまするだけの耳障りな台詞だ。
お父さんに尋ねた事がある。お父さんは鉄棒出来てた?
もちろん。
真実は定かでないが、健二は逆上がりが出来ないのを遺伝のせいにするつもりはなかった。子供にとって、親父はいつまで経っても越えられない壁であって欲しいものだ。
だが、健二も経験する時が来る。親父の背丈を越えた時の虚しさを。人混みに紛れた時の親父が、ただの通りすがりのヒト一人にしか見えなくなる事を。
ある時、幼なじみの明美の家でテレビゲームをしていた健二は、明美に聞いてみた。
逆上がり出来る?
明美はあっけらかんと答えた。
出来ないよ。でも、出来ても何の得にもならないじゃん。
そんな明美に健二は腹がたった。
子供の喧嘩は他愛もないことで始まる。健二は明美を泣かせてしまい、逃げるように家に帰った。
その日、お母さんからその事を咎められ、健二は悔しかった。逆上がりが出来ない方が悪いのに、自分は努力してるのに、どうして……
テレビを家族で観ていた時だった。
ニュースで政治家の汚職問題が報じられていた。それを観ていたお父さんがボソッと呟いた。
『エリートはろくな事しないな。健二、あんなふうになっちゃダメだぞ』
頑張り屋さんの健二にとって、努力=エリートになるのを否定されるのは致命的だった。
それを、尊敬している親父から言われたのであれば尚更だ。
健二は逆上がりが出来ないのをよしとした。
子にとって、親の言動が悪影響を与える事さえあるというのを、健二が気づき理解するには、あと二十年はかかるだろう。
しかしその時には、あれだけ頑張っていた逆上がりの《さ》の字も忘れているだろう。
(1999年初出 超短編小説)
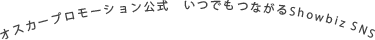

 Login
Login 0 いいね
0 いいね クリップする
クリップする マイアミ―になる
マイアミ―になる









コメント
いいね・コメント投稿・クリップはログインが必要です。
ログインする
不適切なコメントを通報する