1883年に発表されたモーパッサンの代表作で、フランスリアリズム文学の傑作に数えられます。他のモーパッサンの著作には「脂肪の塊」などがあり、短編を多く描いた作家ですがこの「女の一生」はモーパッサンが10年の文学創作活動で6作程度しか書かなかった長編の一つです。志賀直哉はモーパッサンに短編を用いた創作方法を参考にしたといい、「自分の能力が足りなくても文章を短編の枠に当てはめればなんとか形になった」ということです。何をおっしゃいますやら、という感じですが名文は1日にしてならず、なのかも知れませんね。
修道院で教育を受けた清純な貴族の娘ジャンヌは、ジュリアンと出会い胸をときめかせ一生に残る美しい感情を抱きほどなく期待に胸躍らせ結婚します。
しかしジュリアンの愛はほどなくして無関心になり彼は手伝をはらませたり、ジャンヌの親友であった公爵夫人と夜な夜な愛を育んだりします。
後述しますがジュリアンと公爵夫人が同時に亡くなってしまうと彼女は息子に依存し異常なほど愛を捧げるのですが、成人すると彼は堕落仲間の女性と家出のような形で蒸発します。
借金をこさえ、ジャンヌの孫となる娘が出来てしまい引き取り手がない息子に助け舟を求められたジャンヌはパリへ向かいますが息子には会えません。
帰ってきたジャンヌは精神も不安定で炎を毎日ゆらゆら眺めながら過去を思い出し、いつからどうして歯車が狂ったのかなどをぼんやりと思います。
最後は、息子の娘がジャンヌの下に届けられ、ジャンヌは息子、そして裏切られても一生の思い出であるジュリアンの面影に心震え生きがいを感じるシーンで終わります。
残酷なシーンや理不尽なジャンヌ以外の人々、出来事を次々に重ねるのですがスキャンダラスを安っぽい小説の値打ちに用いない意思があるのが好きですね。僕が友達が死ぬより苦手な小説の性描写も出来事は多いですが描写が抑えられています。
トルストイは人間の温もりに対して否定的である、などとして最初この小説を嫌い後に素晴らしいと評価したらしいですが、少ないかも知れませんがジャンヌを中心とした登場人物の、小さな些細な事で現れる人間の素晴らしさというものがこの小説に緩急を作り値打ちを与えていると思います。本当に残酷なだけの小説なら愛せないですものね。
この小説の最後の言葉、孫に対面したジャンヌに対する手伝ロザリの「世の中って、ねえ、人が思うほどいいものでも悪いものでもありませんね」
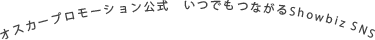

 Login
Login 0 いいね
0 いいね クリップする
クリップする マイアミ―になる
マイアミ―になる








コメント
いいね・コメント投稿・クリップはログインが必要です。
ログインする
不適切なコメントを通報する